宮川崇展
2007年5月12日(土)〜5月26日(土)
12:00〜22:00
 
※ 5月12日(土)18:00〜
宮川崇パフォーマンス
オープニングパーティー 参加費2000円
展示

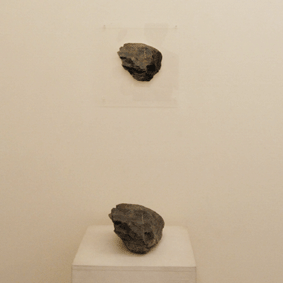
宮川崇パフォーマンス

LINER NOTES VOL.1
宮川 崇インタビュー
意識の証明――《空箱》を巡って
(2006年8月インタビュー・構成/美術ライター・岡部万穂)
2006年7月30日〜8月13日
スペースU企画(タカユキオバナ主宰)
「宮川 崇展」についてのテキスト
01
――宮川さんの作品は、2000年に銀座のギャラリーQでの個展で発表された《無題》(ph00)という作品が強烈でした。正方形の大画面の中に無数の記号を一焦点に収束していくという画面でしたが、遠近法の効果もあって、距離というよりはものすごいスピードを感じました。しかし今思うとあれは一つ世界があるとしたら、その入口に立ちながら同時にその終わりも見ている、というそんな視点でもあったのではないかと思うのですが、あれはどんなイメージで作ったのですか?
宮川 遠近法を使い、消失点に向かって面が無限に遠ざかるように見せるのは、イメージというより方法として選択したものです。まず最初にオリジナルの記号を作るという過程がありました
(ph01)。それは《無題》にタイルのように貼りつけてあるものですが、その当時は……言葉による伝達ということに非常に絶望感を感じていた時期で、構造主義の言語学の本を読んだりしていたのですが、その中に“言葉というものは差異による体系であって、言葉そのものの根拠は何もない”
ということが書いてあり、とても衝撃を受けたんです。それは長年の言葉に対する自分のわだかまりを解決してくれる考え方で、目からウロコが落ちるとともに、より伝達に対する絶望感が大きくなるものでした。自分だけのオリジナルの記号を作ったのは、その衝撃を絶望感とともに何らかのかたちではきだしてしまいたいという個人的な動機だったと思います。
それらを個展のときに一つのパーツとして用い、遠近法を使って配置することを、記号自体の無意味さからそれを使ったコミュニケーションの可能性を探る方向へと自分を向かわせる“方法”として選択したと思います。
自分の位置から次の位置に行きたいという意志みたいなものというか、空間に設置することによって、無意味さを乗り越えられるような気がしたんです。
――言葉による伝達に、なぜそれほどまでに絶望
感を持っていたのですか?
宮川 子供の頃からですね。対人関係をうまく築くことができなかったり、自分の考えていることも他人にはわからないし、他人の考えていることも自分にはわからないという意識が強くあったんです。ただ、いろいろなことがわかる年齢になってくると、もっと具体的なことで思い悩むようになり、皆そうだと思うのですが、自分もいろいろ思い悩んだすえに「自分は何かを理解していないからこんなに苦しむのだ」と考えるようになり、そこで何か答のようなものがどこかにあって、それを知ることによって具体的な解決法が得られるんじゃないかと思ったんです。それでまずいろいろな本を読んだのですが、無数の言葉の中には、答のようなものは一向に見つからないんです。そんなときにソシュール(注0)の構造主義言語論に出合い、“言葉は絶対的な答を描写できない”という理論を見つけたんです。これは自分なりのかなり乱暴な解釈なのですが、でもそれでかなり楽になりました。
――同時期に《Emptyness》(ph02)シリーズを作っています。遠近法を使った構造は《無題》と同じですが、無題が一つの世界を探る出発点だとしたら、これは人間の意識体系のようなものがより具体的に視覚化されているように見えます。たとえば立体だと思っていても実際は平面であるとか、平面の中にも立体感が含まれるというような、意識の多様性の部分を視覚化するという試みだったんじゃないかと思うのですが、こちらのシリーズではどういう意識だったのですか?
宮川 そうですね。これは《無題》の曼荼羅の次に出てきたシリーズなのですが、無題のシリーズによって今まで平面を平面として扱ってきた作品から、“奥行き”という絵画的なイリュージョンが出てきたんです。実際に空間はないのだけれど、空間に見える効果を、いわば意図したわけではなく偶然手にしたわけです。最初の個展のときに、今まで記号として完全に二次元として扱っていたものを、三次元的というか、一つのタイルのようなものとして扱うことができるようになって、そのタイルという構成要素によって新しい構成物を作り出すことができることを発見したんです。最初の個展でもいくつか試してはいるのですが、つまり二次元的に使っていた記号を、遠近法を使って歪めるということをやり始めてから、二次元的世界を三次元的に拡張することによって、二次元的な制約を乗り越えることができた。ただ、それもあくまで平面だけど立体に見えるという疑似三次元ですが、しかし平面でありつつ立体という両極端の要素を兼ね備えているという曖昧な状態、つまり“実体がない”という状態がストレートに見えている。言語のように、人間の実体のない精神活動のようなものが視覚的に現れた一つのモデルだと思ったんです。
――絶望の発見から、絶望を形にして眺めているという視点に変わったわけですね。
宮川 つまり構造主義の考え方も、やはり言葉で説明されているわけですよね。言葉のことを言葉によって説明しているということは、実体のないものを実体のないものによって説明するということで、その矛盾は解決しきれない。しかし実体のない人間の精神活動が、言語化ではなく視覚化されたと思ったんです。
――その発見は精神構造にどんな影響を与えま
したか?
宮川 それは大きかったですね。まず言語という実体のないもの、人間の精神活動全般といっていいと思うのですが、そういうものにかたちのとっかかり、目で見てわかるとっかかりを、自分の思考によってかたちづくることができるという可能性を感じたというか、つまりかたちにできるということに希望を持つことができたのです。だから一番最初の作品からemptinessへの道は、既に開かれていたのかもしれません。《無題》と《emptiness》はほぼ同時期に制作したものですが、非常に早い時期に次のシリーズができて、最初の作品の総括になったと思います。
02
――次は2001年に吉祥寺のギャラリー人(現在は谷中に移転)で発表した《1/無限》(むげんぶんのいち)(ph03)シリーズになっていくわけですが、これは一つの立体モデルを作り、それをあらゆる角度から撮影し、パネルに貼って展示するという作品でした。ちなみに写真は何枚くらい?
宮川 使わなかったのを含めると500枚くらいですね。
――前回のシリーズで、“実体のないものは視覚で表すことができることに希望を持った”と言っていますが、あの赤い立体は、そうした目に見える世界を象徴するかたちだったのですか?
宮川 あれは、ある幾何学形態を扱った本に一つのわかりやすいモデルとして載っていたのをアレンジしたもので、あのかたちにピンときたのは、まずシンメトリーではないこと、それが見る角度によって相当違うかたちに見えるだろうと思ったことです。そういうものを求めていたときに偶然目にして、それを採用したということです。
――ものすごくいろいろな角度から見ていますが、世界の見方が明らかにこれまでと違いますね。あらゆる角度から見るという視点はどういう流れから出てきたのですか?
宮川 《emptiness》シリーズで疑似三次元を作るようになってから、実際の三次元の幾何学形態に興味を持ちはじめて、自分でも立方体の枠を作ってみたりしていたんです。実際に立体を作ってそれを手に取って眺めているうちに、一つの幾何学形態が見る角度によってシルエットがいくらでも変わるという当たり前のことが分かったんです。
――意識的に立体を作ってみたのは初めてだったわけですね。
宮川 そうですね。三次元とは何かという意識を持って作ってみたのは初めてでした。《1/無限》では、一つの思考というものが“見えるもの”になったんです。たとえば立体は、「一つの角度につきそれぞれ一つの見え方がある」という説明を言葉ではすることができます。でも実際に立体を手に持ってくるくる回しながら見ていたとしても、一瞬その角度から見た見え方は、次の別な角度から見ているときには見ることはできない。つまり実際は、「常に一つの角度からしか見ることはできない」わけです。だけどそれをさまざまな角度から写真に撮ったものを並べて見せれば、一つの立体をさまざまな角度からいっぺんに見ることができる。そういう状態を作ることができるなと思ったんです。人間の精神活動は一つの物体をいろいろな角度から見た視点を総合的に把握して解釈するわけですよね。しかしそれは頭の中で行われていることであって、その精神活動を目にすることは本来ないわけです。だけど、あらゆる角度から見た形を同時に展示することによって、精神活動が視覚化される。《1/無限》では、実体のない精神活動をまた異なる方法で視覚化することに成功したと思うんです。
03
――これまでは、精神活動といったどちらかというと内的宇宙の作品に見えていたのですが、次に風景や宇宙、空などの写真を立体に貼りつけて見せるという作品(ph04)になっていきます。このあたりからは内的な視線はだんだん世界全般を、宇宙全体を見ていくという視点に移って行ったように見えるのですが、このあたりの展開について教えて下さい。
宮川 幾何学的な形態に写真を貼ったということで別の展開を見せることができたと思います。
《1/無限》の発表で、自分自身とても印象に残ったのが、相反するものが同時にそこにあるという状態は言葉によって描写することはできないけれども、常に人間の認識の根本にあるものなのではないかということでした。それは多分自分が最も重要なテーマだと思っていることだと思うんですけども、世界というものは非常に多様で、ある一つの視点から見ただけではわからないものであり、同時に相反するものが共存している状態がむしろ普通なんじゃないかと。要はそれがこの世界の重要なルールなんじゃないか。それは言葉では描写しきれない。そんな意識を《1/無限》のときに明確に持ち始めたんです。
――世界観が確立されたわけですね。
宮川 そうですね。それで終わりではないですが。最初期の“立体だけど平面”というような相反する要素を、今度はより幅広く兼ね備えさせたいと思うようになったんです。《1/無限》は写真を切り抜いて貼ったものですが、疑似三次元という意味ではこれまでと変わらなかったわけです。そこで相反するものを兼ね備えているモデルとしての疑似三次元を、三次元の側からとらえられないかということを考えはじめたんです。つまり今までは二次元世界に三次元的な要素を視覚的に導入するという方法でしたが、逆に三次元世界に二次元的な要素を入れることによって、新しい疑似三次元を作る出せるんじゃないかと。三次元を二次元化する、つまり疑似三次元というあいまいな状態への、別な角度からの挑戦というか。それで幾何学的なかたちに写真を貼るということを考えて、それが炎や星空や空になったわけです。炎や空は、いわば人間の目が知覚するイリュージョンだから、それは無限に続く遠近法の画像と性質は同じだと思うんです。
――宇宙や空を幾何学形態に貼るという方法は、ものごとは相反する要素があるという世界のルールを証明するための作業というわけですか。
宮川 相反するものがより離れたものであればあるほど、それを一緒にしたときの衝撃力は大きい。今までの要素からより拡張し、より遠く離れた要素を一つにしたいと思い、空や炎を、自分からより遠いものとして選んだわけです。
――これらは単純に美しいですね。
宮川 調和ということ自体が美しいということも言いたかったので、その意見はうれしいです。
04
――今回の“空箱”シリーズ(ph05)は衝撃でした。マジックミラー、発光ダイオードなど、鏡と光を使った作品です。マジックミラーは外側の光源の中では、中を見ようと思っても見えない。しかしあたりが暗くなり内側から発光すると初めて内部が見えるという構造ですね。今までと比べると、これらは自分自身の意識の内部を見るような気がするのですが。
宮川 鏡というのは2枚を向かい合わせにすることによって、その間で映像の増幅が起き、映されたものが無限に見える。鏡はきれいに光を反射することによって実際に目の前にあるものが映る非常に面白い物体だと思うんです。鏡という二次元的な板は三次元の無限の広がりを視覚的に作り出す装置になる。それはつまり“閉じた世界”と“無限の広がりを持つ世界”という相反する要素が同時に起こっている一つの重要なモデルであるとずっと思っていたんです。それは自分の作品のテーマと非常に近しいところにあって、それは宇宙とか炎といったシリーズの頃に非常に強く思っていたことです。最初に、鏡を立方体に組み立てて正六面体の内部が合わせ鏡になった状態を作り、全方位無限空間という状況、つまり限定された空間の中に疑似無限を作るという構想がありました。それもやはり疑似三次元ではありますが、一つの思考モデルとしてぜひ手がけて見たいと思ったんです。最初は鏡の立方体に穴を開けて中を覗くという試作をしたのですが、それだと覗いている自分も見えてしまい、無限に広がる空間の中の一部しか覗けないというフラストレーションがありました。その問題点を解決するためには、自分が巨大な鏡の箱の中に入ってしまえばいいと思ったのですが、技術的に無理でした。しかし合わせ鏡による疑似無限のエッセンスを何とかして作りたくて、6面のうち1面だけをマジックミラーにして1面全部を覗き穴として使う方法も考えたのですが、それもやはり根本的な解決ではなかった。それで6面マジックミラーができたというわけなんです。それを《空箱》と名づけて一つの思考モデルとして展示したわけです。
――空箱というネーミングは?
宮川 般若心経の“空”からですね(注1)。「からばこ」とも読めます。この作品は箱の中の閉じられた空間であり同時に無限であるということと、実体のないという“空(くう)”をひっかけて名づけました。ちょっと気の利いた愛称をつけたかったんです。
――《空箱》は、中間的な要素がたくさんありますね。ボルトもやたらと大きいし、色彩に赤や青の色がある。また、対向する壁面に小さな鏡が向かい合わせに設置されていて、片方の鏡には光が当たっているという作品がありました。この光源自体も疑似無限を照らすための装置にすぎないのでしょうが、しかし片方の鏡に光を当てると、その光は向かい側の壁に反射し、さらに向かい側に設置してある合わせ鏡はその光をさらに反射する。合わせ鏡の間に光を設置することによって新たに生まれる関係性など、空箱のコンセプトとはおそらく無関係な部分の要素も気になるところでした。宮川さんの作品はとてもミニマルですが、これらのはからずも現れた要素には、非常に叙情的なものも感じました。(ph06)
宮川 コンセプチュアルアートの作り方として、ある一定のルールにのっとって制作をしていると、その過程には意図しなかった効果が必ず現れるということがあります。それをサイドエフェクトといい、次の作品はそのサイドエフェクトを使用して作る。するとさらに違うサイドエフェクトが生まれ、またさらに次にも生まれる。そうやって永遠にサイドエフェクトが生まれ続けるという方法論を学んだことがあります。その考え方にとても感銘を受けたのですが、つまり精神活動を物質として作ってみると、今言われたみたいな“壁に映る影”といった、予想外の効果が生まれる。それは精神活動内で処理していたのでは絶対に生まれないものがあるということを示しているのだと思います。
私は世界は非常にわかりやすく明らかなものだと思っていて、大きなボルトにしても、接着しやすいということと、より構造を明確にするために使っただけなんです。私は基本的に何かを暗示したり、謎めかしたりしたくないんです。というのも、この現実が存在していることそのものが最大の謎だからです。世界七不思議が不思議なんじゃなく、世界があることが不思議なんです。宇宙があって、生物が生まれて、なぜそういうことを考える人間がいるのか。なるべく明らかな方法をとることによって謎を顕在化させるというのが自分の方法だと思っています。
――色や光といった要素についてですが、異なる要素の共存という法則にのっとって考えると、精神に相反する要素は肉体あるいは感情といったものになるのでしょうか。少しテーマとは外れる質問ですが、精神を箱というミニマルな物質へと凝縮していく過程の中で、肉体や感情といったものは削ぎ落とされていく要素ですか。
宮川 精神に対する要素というのは、肉体というより物質全般ですね。自分にとっては作品がある意味肉体です。つまり物質化されるということは肉体との接触を意味しているんです。手に取ったりその気になれば舐めたりすることもできる。作品を作るうえで、まず肉体があってということではなくて、どうしたら物質の世界と記号的な世界をつなぐことができるかということを常に考えています。作品自体はミニマルなものですが、削ぎ落としているというつもりはないんです。あくまでもイメージですが、自分の作品は精神活動と物質がつながる特異点(注2)であるというふうに考えているんです。精神と物質の間にある連絡口のようなものでしょうか。
補足
「“自分自身”のことなど考えていたら死んでしまいます!」
学生時代、現代美術の講義の中で李禹煥は叫んだ。モノ派の教授が教鞭を取り、先時代のアートの残り香を90年代の空疎の中で辛うじて食み、空の中から錬金術のように表現を模索する学生時代を過ごしたのが70年代生まれのアーティストたちだろう。「暗示を排除し、明らかな方法をとることによって謎を顕在化させる」方法論や、精神と物質の間の特異点といった、精神と物質(肉体)を個別に捉える視点など、彼の作品はミニマルアートに続くコンセプチュアルアートの先人たちの影響を強く受けつつ、自己自身の表現という純粋
芸術のあり方を否定し、作品そのものの物質性や表現性を排除することによって思考を解放しようとする先人たちの方法論から宮川が編み出したのは、自己の思考そのものを物質として提示し、さらに自己へと還元しながら世界を発見していく方法だった。
思考モデル=構造の提示は、人間の思考が世界を開き、変え得るという一つのモデルでもあるのではないか。
(注0)フェルディナン・ド・ソシュール:言語学者・言語哲学者。言語を体系ではなく構造として捉える言語理論は、のちに記号学を生み、記号学は構造主義の礎となった。
(注1)般若波羅密多心経における「空」:原語シューニヤター。「何もない状態」の意。インド数字では「ゼロ(零)」の意。
(注2)特異点:作者は「ビッグバーンの最初の凝縮された1点」という宇宙物理学的意味合いで使っている。ここでは詳述は省く。
宮川崇氏が主宰する現代美術ユニット「ん」
http://www.studionn.com/
このページの先頭へ
|

